10【重要】相続税の『基礎控除額』はいくら?申告が必要かチェックする方法
【重要】相続税の『基礎控除額』はいくら?
申告が必要かチェックする方法

「相続税は富裕層にかかる税金だから、自分には関係ない」—そう思っていませんか?
実は、平成27年(2015年)の税制改正により基礎控除額が大幅に引き下げられて以来、日本の相続税の課税対象となる人の割合(課税割合)は約2倍に増加し、現在では「10人に1人」が相続税を納めているのが現状です。
特に、自宅(不動産)をお持ちの方や、ご家族の人数が少ない方は、相続税の申告が必要になる可能性が高まっています。
この記事では、相続税の申告が必要となる概算ラインとなる「基礎控除額」の計算方法と、申告の要否をチェックする簡単な方法を解説します。
相続税の申告義務を判定するボーダーライン「基礎控除」とは?
相続税の計算における「基礎控除額」とは、相続した財産の総額から無条件で差し引くことができる非課税枠のことです。この非課税枠が、相続税の申告が必要かどうかを判断する最も重要なボーダーラインとなります。
基礎控除額の計算式
相続税の基礎控除額は、法定相続人の数に応じて以下のように計算されます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
この計算で求めた基礎控除額を、相続した財産(プラスの財産から債務や葬儀費用を引いた「正味の遺産額」)が超えない場合は、原則として相続税はかからず、申告も不要となります。
逆に、基礎控除額を超えた場合は、超えた部分に対して相続税が課税され、原則として相続税の申告が必要になります。
【早見表】法定相続人別の基礎控除額
ご自身の法定相続人の数を確認し、まずは申告ラインの概算を把握してみましょう。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額の計算 | 基礎控除額 |
| 1人(例:配偶者のみ) | 3,000万円+(600万円×1) | 3,600万円 |
| 2人(例:配偶者と子1人) | 3,000万円+(600万円×2) | 4,200万円 |
| 3人(例:配偶者と子2人) | 4,800万円 | |
| 4人(例:配偶者と子3人) | 3,000万円+(600万円×4) | 5,400万円 |
相続税の申告が必要か?簡単3ステップチェック
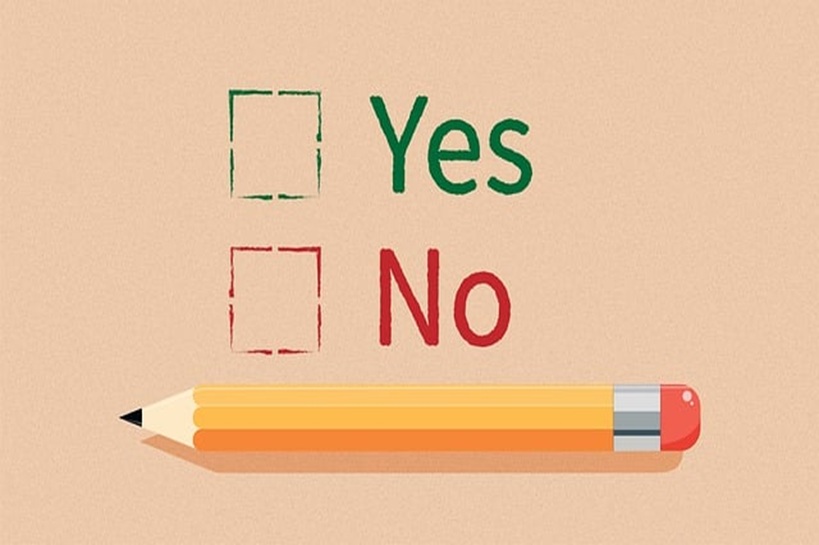
「私の財産は基礎控除額を超えているだろうか?」と疑問に感じたら、まずは以下の3つのステップで概算チェックをしてみてください。
ステップ1:「みなし相続財産」を忘れていませんか?
相続税の対象となる財産は、被相続人(亡くなった方)が所有していた預貯金や不動産だけではありません。特に注意が必要なのが「みなし相続財産」です。
・生命保険金
・死亡退職金
これらは民法上の相続財産ではありませんが、相続税の計算上は財産に含める必要があります。
ただし、それぞれに非課税枠が設けられています。
ステップ2:「正味の遺産額(概算)」を計算する
すべての相続財産(不動産、預貯金、株式、みなし相続財産から非課税枠を引いたものなど)の合計額から、借入金などの債務と葬儀費用を引いた金額(正味の遺産額)を概算します。
ステップ3:基礎控除額と比較する
ステップ2で求めた正味の遺産額(概算)と、ステップ1の表で確認した基礎控除額を比較します。
| 比較結果 | 相続税の申告の要否(原則) |
| 正味の遺産額 ≦ 基礎控除額 | 申告・納税ともに不要 |
| 正味の遺産額 > 基礎控除額 | 申告が必要(納税義務発生の可能性あり) |
要注意!「相続税ゼロ」でも申告が必要なケースとは?
上記のステップ3で「申告不要」となった方でも、例外的に申告が必要となるケースがあります。これは、相続税の税額を劇的に軽減する特例を利用する場合です。
これらの特例は、適用を受けることで最終的な相続税額がゼロになったとしても、特例を利用したこと自体を税務署に申告書で伝えなければならない、と法律で定められています。
申告が必須となる主な特例
-
配偶者の税額軽減(配偶者控除):配偶者が相続した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分相当額の、いずれか多い金額までは相続税がかからないという特例です。
-
小規模宅地等の特例:被相続人の自宅の土地や事業用の土地について、**最大80%**の評価額を減額できる特例です。この特例により、不動産の評価額が大きく下がり、結果的に基礎控除額以下になるケースが多くあります。
相続財産が基礎控除額を超えている方は、これらの特例を適用することで納税額をゼロにできる可能性が高いです。しかし、特例の適用には遺産分割協議が成立していることなど、いくつかの要件があります。

